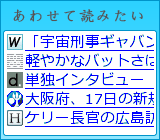これから話す内容は、自分の生業の要である“発想”についての体験をリバースエンジニアリングして図示するとこうなりますという類の物であって、これが真理だとか唯一無二だとか言う話ではありませんのでご了承ください。
発想(アブダクション)とは、思考の再生産であり連想そのものである。人間はゼロから発想する事が出来ません。故に連想なのですが、生まれ持った自身の本能と外部からの環境情報を結び付け知能が発達して行きます。
その際の記憶も又、連想で紡がれて行きます。
そして世代を重ね乍ら脳のキャパシティをアップグレードして来ました。
さて、発想をするに当たって私は大きく6つの要素に分類しております。
図に在る様に上から順に説明して行きますが、先にお話しした様に発想をするには予め連想先の情報の下準備が目下必用になって来ますし、又その仕込みの為の前技といった要素が6つ目の連想に至る前に5つ存在すると理解頂けると把握し易いのではと思います。
 モチベーション(意欲)
モチベーション(意欲)
動機が何であれ、これが無ければ始まりません。
イニシエーション(通過儀礼)とベンチレーション(換気)のプリショットルーチン
プリショットルーチンとはゴルフショットの前に個々で行われるパターン化された決まり動作の事です。
つまり練習の時と何ら変わらない普段通りの一緒の行動を取る事で、特別な舞台での精神的プレッシャに押し潰されない様に扁桃体の示す恐怖感を大脳記憶の論理的にも説明し易い日常動作イメージと摺り替えるメソドです。
大リーグのイチロー選手が、バッターボックスに入ってから行うバットを垂直に立て袖を引くといった一連の動作もそうです。
尤も、スポーツの様なプレッシャは無いわけですが、殊発想に於いてはリラック状態でふらふらしたりぼけっとしている方が着想し易いので、突然の急ぎ仕事に見舞われたいざという時の保険です。
その一つが自分なりの
イニシエーション(通過儀礼)と、汚れた空気を酸素を沢山含んだ新鮮な空気を取り込む
ベンチレーション(換気)です。
当初はこんな話しを長々とした所で誰も耳を貸さないだろうし、エネルギーの無駄で一人馬鹿を見てるみたいで何だか恥ずかしかったので自分だけの秘め事にしていたのですが、NHKの番組で宮崎駿が仕事場に挨拶し換気するという自分と全く同じルーチンをこなしていたので載せました。
流石、民俗学に精通した人間はわかっておられる。
スポーツ選手もグラウンドに挨拶していますよね、あれと一緒です。
こうした話は後のインスピレーションの項で話します。
コレクション(収集)
集めるという行為は、動物にとって餌を獲り蓄えたり草木を身に纏ったり住居の一部にするといった生きる事に直結する本能的行為です。
人間は知能が発達し物質から物質の情報、情報その物へと指向して行きました。
しかし多くの答えはそれを育んだ物質たる自然環境に多く存在していると思います。
オブザベーション(観察)
集められない物はその場で観察し情報収集となり、観察がその侭連想に直結する事も多いので、五感をフルに活用して認知する事が求められます。
アソシエーション(連想)
さて様々な下拵えをした所で愈々連想という本題に入ります。
連想には「意識」「前意識」「無意識」という大きく分けて三つの深度からなる意識レベルが在り、上位の意識を基準に不規則に行き来していると捉えております。
ただ誤解してほしくないのは、深ければいい情報に出会えるというわけではないという事です。
確かに深く迄アクセス出来れば広がった分だけ情報帯域が拡大するわけですが、実際は深度が増す程アクセス出来る滞在時間が短くなり、それも意識レベルの浅い所迄如何に引き上げられるかという釣りで云う所のフッキングの能力に大きく左右されます。
その能力をアップする方法については、又別の回で触れたいと思いますが、要するに図示している様にその意識レベルとは肯定法による瞑想によって到達しようとするレベルその物だという事です。
アスピレーション(大志,吸引)
汗水垂らして努力すれば誰にでもチャンスを掴める連想活動という事になります。
深度が浅く意識がハッキリしている状態で、相対的に自分の深度の立ち位置を認知する上でも基準となる重要なファクターであり、思考の芯がブレない様な大枠たる大志、マインドマッピングで云う所のセントラルイメージを保ちつつより深い意識レベルから吸引、そして吸い上げた情報を統合するという役割を担っています。
インスピレーション(霊感,着想)
人間が未だ死と隣り合わせだった時代、生死と向き合い生き存えようとする智慧を得る為に、神という概念を自然環境による生命力という観念の外部情報からインスピレーション(
霊感)を得た、即ち精霊として感じ取りました。それが想像(イマジネーション)が着いた瞬間の入り口たる
着想です。
そしてその生命力とそれを感じ取る能力を「霊力」と呼び、様々な事象から真理を見抜く“
帰納(インダクション)”、又逆に数限られた事象から様々な事を見通す“
演繹(デダクション)”、総じて「悟り(リアリゼーション:認識)/覚り(アウェイクニング:覚醒)」と呼びました。
イマジネーション(想像,空想)冒頭のアソシエーションで申しました様に、どんなに想像や空想をしてもその領域から意識下に引き揚げる際にその記憶の断片も掴んで引き上げられなければ収穫はゼロです。
インスピレーションからの延長で直観に於ける様々な記憶を結合し統覚による統一像、即ち想いが像として脳裏に映されている
想像の自覚がある内は意識レベルは人並みで安全圏すが、空へ想いが解き放たれる
空想からその状態すら全く自覚、認知出来ない「(意識下へ)帰って来れない」という
解離の状態に迄連想が大発散してしまった場合は、最早現実との区別が付かない事を意味するので大人であれば危険です。
そういう意味で空想を表現としてアウトプット出来る芸術家は、それが薬物に因る物でなければ精神異常と紙一重の能力の持ち主と言えるでしょう。
さて、三つの連想について話して来ましたが、それが理解出来ると右隣に例として記した「
1(1人)」「
1対n(1人対複数)」「
n(複数)」によるアイデア出しの位置付けも理解頂けるのではと思います。
ホットリーディングと
コールドリーディングが入っているのは、結局連想というのは既存の情報に基づいた推理や推測とも言えるわけで、それを受け取った側の解釈次第で発想によるアイデアだとか、それこそ霊能力による霊視であるとか変わって来るのだと思います。
私なんか目を瞑ってじっと人の話を聞くので「オーラの泉」だとか、時には空寝(そらね)と言ってクライアントが会議してる傍らで横になって寝たフリをし乍ら参加してるので「チャネリング」と呼ばれています(笑
仕事の話ついでにもう少しイニシエーションとベンチレーションについて掘り下げると、前者が名刺交換、当方は名刺を持たないのでアイデア提示、後者が第三者の介入という社内の風通しを上げるコンサルティングとなります。
所で宮崎駿の条、理解出来ましたか?
インスピレーションを働かせてみてください。
では、そうした件も含めて纏めに入りたいと思います。
猿が人を創造し、人が神を想像した。故に人間の最初の想像の産物である神を十分理解しリスペクト、即ち自然に敬意を払い大切にしなければなりません。
そしてそれが出来るのは、先進国に於いて土着信仰を神仏習合の前者、即ち神道として確立している日本人だけであるという事、他国は日本で言う所の外来宗教である仏教に相当する哲学系宗教という後者しか持ち合わしておりません。
従って先進国に位置し乍ら土人文化の荒々しさと制約無き発想力を持ち合わせる日本という国で生まれ育っただけで、十二分に恵まれているし勝ち組なのです。
発想はお金が無くても出来ます、そして発想を出来ない人からお金を頂けます。